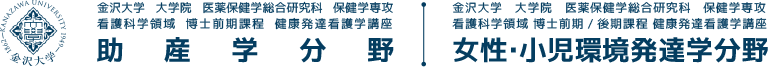2023年度
助産学分野1年(M1)
2023年4月に5名の新入生を迎え、半年が過ぎました
1年次の前半は、主に講義や演習から助産学の基礎的な知識や技術を習得します。
そして、今年は、7月に母性育児支援実習(助産学実習Ⅰ)、9月には、初めての分娩介助実習(助産学分野Ⅰ)を行いました。
助産学実習Ⅰを終えて思うこと
分娩介助実習では、妊産褥婦さんや赤ちゃんと直接関わらせていただき、分娩各期における産婦さんの身体的変化や痛みに対する反応の変化などを一番近くで感じたり、助産師さんたちに助言をいただきながらアセスメントやケアを考えたりすることができ、大変貴重な経験になりました。実習中は初めてのことばかりで不安や戸惑いもありましたが、日々できることが増えたり、お母様方から感謝のお言葉をいただいたりすることができ、充実した1か月間となりました。
母乳育児支援20時間コース基礎セミナー
今年も、粟野雅代先生(IBCLC:国際ラクテーションコンサルタント)を講師に招き、母乳育児支援に関する研修を受けました。6月から10月にかけて4日間に渡り、知識だけでなくコミュニケーションスキルに関する学びを深めることができました。
また、6月から10月の間には、母乳育児支援実習(助産学実習Ⅰ)・分娩介助実習(助産学実習Ⅰ)があり、実際にお母様や妊産婦様と関わる経験をしながら、研修を通してさまざまなことを感じ、考え、学びを深めてきました。



実習や研修を終えて思うこと
講義で母乳育児支援をしていくために必要な基礎的な知識を身につけ、ロールプレイや実習を通してコミュニケーションスキルについても学びました。実習では実際に母子と関わる中で、その方の思いや状況に合ったケアを考えて実施しました。ケアを通してお母様方が笑顔になってくださったり、退院が近づくにつれて母乳育児が確立されていく様子が見られたりして、やりがいを感じることができました。この研修を受けることで、国際認定ラクテーション・コンサルタント(IBCLC)認定のための単位を一部修得することができ、今後の学習意欲にもつながります。
地域助産実習
石川県内の小・中・高校で「生と性の学習会」に参加させていただきました。
講師は星の子助産院の坂谷理恵子先生です。
地域で活動する助産師が「いのちと性の教育」を行う事の意味や、思春期にある学生さんたちの発達段階や多様性を理解しながらセクシャリティやいのちの大切さを伝える教育技法を学ばせて頂きました。

(坂谷先生からのご講義に参加)

(妊婦体験のサポート)

(新生児人形の抱っこ体験のサポート)
あけぼの子ども園「Life活動」
星の子助産院の坂谷先生のご指導のもと、あけぼのこども園の『Life活動』にボランティアとして参加をしてきました。「いのちのおはなし」をテーマに4〜5歳の園児たちと、どうしたら一つ一つのかけがえのないいのちを大切に出来るかを一緒に考えてきました。園児たちのとても可愛い反応に、学生たちも終始笑顔で楽しい時間を過ごすことが出来ました。
あけぼの保育園のみなさま、坂谷先生、ありがとうございました。


(園児たちが見つけたいのち) (子宮内で胎児が大きくなる様子を紹介)


(子宮内の胎児の様子を紹介) (あかちゃんの抱っこの方法を紹介)


(あかちゃん抱っこ体験のサポート)


(手の大きさを比べっこ)
出産教育・コンサルテーション
2つのグループに分かれ、それぞれ助産学生役、妊婦役になって出産準備クラスを企画・ロールプレイをしました。地域で思春期クラスをされている坂谷先生にご助言をいただき、たくさんの学びを得ることができました。
Group1 : おっぱいクラス 〜赤ちゃんとの生活に向けて〜



◯クラスを計画し実施して感じたこと・思ったこと◯
母乳の利点を書いたカードを使って参加者と交流しながらクラスを進行したり、赤ちゃんモデルを活用して授乳姿勢の説明をしたりと、参加者が楽しみながら母乳育児について学べるようにクラスを企画していきました。また、参加者が歓迎されていると感じられるように事前に配布物を作成したり、会場の雰囲気を作ったりしていくことも大切なことであると学ぶことができました。様々な発達段階にある方々に対してクラス運営を行っている坂谷先生からご助言をいただいて、自分たちだけでは気づくことができなかった視点を得ることができました。出産教育は助産師として妊産婦への支援を行ううえで必ず必要になるため、坂谷先生からいただいたご助言をもとに今回の学びを将来にも生かしていきたいです。
Group2 : 家族でやろうエクササイズ 〜出産に向けた健やかなからだづくり〜



◯クラスを計画し実施して、感じたこと思ったこと◯
クラスの企画の段階では、対象者をどうするか、目的と内容の一貫性をもたせるためにどのように工夫したらよいか、妊婦さんが安全に行える運動は何か、一緒に参加してくれるパートナーとの交流を運動の中でどう取り入れるかという点を考えるのが難しかったです。実際に実施する中では、一方的にならないように参加者に意見を投げかけ、その意見に対してコメントを返して会話のキャッチボールができるように意識しました。妊婦体操の実践で、見本をみせながら説明し、参加者が安全に実施できるように巡回・声かけするという役割を分担して行うのが難しかったです。
妊婦役としてクラスを受けてみて、実際に妊婦さんになりきることで、妊婦さんに負担の少ない座り方や効果的なクラスの進め方、関係づくりを促進できるコミュニケーションの方法などについてより具体的に考えるきっかけになりました。
坂谷先生からのご助言をいただき、環境整備(部屋の明るさ)やクラス内容の時間配分の点で客観的な視点をもって考えることの大切さを改めて実感しました。いただいたご指導を活かし、今後のクラス運営をより良いものにしていきたいと思いました。
助産学分野1年・2年
助産学分野院生合同ゼミ(1年生・2年生)
1年生と2年生の合同ゼミでは、お互いの研究について意見交換をしています。
12月になり、いよいよ2年生は佳境に入ってきました。論文執筆を頑張っています!

助産学分野2年(M2)
いよいよ、国家試験の日を迎えました!
これまで頑張って勉強してきた自分を信じて、10期生4名が国家試験に臨みました。